梵(ぼん)な道具を聴いてみる。 第九回 大雪:洋に倣った金彩の和ガラス。
未見の懐かしさに溢れた、美の結晶。
(2012.11.28)
「梵(ぼん)な道具を聴いてみる」第九回は、南蛮の空気を存分に吸い込みながらも和の香りが鼻をくすぐる、明治時代の金彩ボトルをご紹介。古いガラスが放つ均等を欠いた華やかさは、そのまま「むかし、という言葉のやわらかさ」と繋がっている気がする。魅惑の和ガラスの世界へようこそ。
最初期の和ガラス。
現存する日本最古のガラスは弥生中期から古墳時代まで遡る。中国大陸から運搬されたガラスの塊を再融、作成し数々の装飾品(ガラス玉)を生産したのが最初といわれているが、材料の調合は中国に依っていたため純粋な和ガラスとはいい難い。しかし正倉院に伝来する「造物所作物帖」の断簡にはガラス原料の調合方法が記されており、早くも飛鳥時代にはガラスの国産化を実現していたことが分かる。正倉院には王妃が身につけたガラス玉や勾玉などの装飾品、双六に使用する玉など数多くのガラス製品が伝来しており、それらは毎年秋に開催される正倉院の展観でも話題に上る。
中世、平安時代から室町時代にかけては上流階級層の装飾品、あるいは宗教遺物等にガラスの小品が見られるものの、源氏物語の「梅が枝」の巻に登場する白瑠璃の杯や枕草子の「うつくしきもの」の段の瑠璃の壷も全て中国からの伝来品である。これは国産ガラスの史上かつてない「空白」であり、事の次第は謎に包まれたままだ。しかし時代は進み、ポルトガルのキリスト教宣教師によって織田信長に献上された<ガラスのフラスコ>に入った金平糖、オランダ東インド会社から持ち込まれたヴェネチアのグラスなど、次なるガラスの魅力が「舶来」という形でやってきた。
和ガラスの成熟。
1600年、オランダ船のデ・リーフデ号が大分の白臼湾に流れ着いたのが縁でオランダとの国交が始まる。その「漂着」から9年後、鎖国時にも拘らずオランダ商館が建設された長崎県出島にはオランダ人(彼らは紅毛人と呼ばれた)により多くの文物、中には望遠鏡や眼鏡などのガラス製品の他、リキュールなどを嗜むためのグラスや徳利、食器などの珍品が「特区」に持ち込まれた。
早速ガラス生産に乗り出した日本人は職人気質で手先も器用。素材の特性を最大限に生かしてあらゆる種類のガラス製品(びいどろ)を作り上げ、裕福な商人を中心に人気を博した。びいどろは、その涼感ゆえ夏の風物詩とされ、しばしば浮世絵のモティーフとしても描かれた。
江戸中期には風鈴や髪飾り、金魚玉や暖簾、建具の類にまでガラス製品が登場し和ガラスの成熟ぶりが見て取れる。更に幕末頃、硬質な透明ガラス「ギヤマン」の製造にも成功しカットガラス「切子」の技法も確立。中でも色ガラスを着せ様々なカットを施す「薩摩切子」は江戸時代最後を飾るガラス工芸品の代表格となった。
しかし、人気の裏舞台で幾つのガラス製品を粗相したことだろう。「びいどろ」や「ギヤマン」は大変に高価な上、割れやすいため使い手には細心の取扱いを要求するが、そこにはガラスの魅力以上に所有する「荷の重さ」は存在しなかったのか。筆を休め少し考えてみると、ある時すっと腹に落ちた。却って割れやすい素材だからこそ、儚さ(=寂び)を重んじる日本人の感性とフィットするのだ。つまりガラスという製品が単に美しいという事のみならず「粗相で一瞬にして粉々になる」というリスクを背負うからからこそ、ここまで愛されたのではないか。「割れやすいが、ガラスにはその欠点をも凌駕する魅力がある」というのは、実はガラスを購うための言い訳に過ぎない。
明治時代の金彩ボトル。
写真の金彩ボトルは明治時代の作であるが、鉛ガラスを宙吹きした後に成形と繊細なハンドカットを施され、そこかしこに幕末の記憶が残っている。ひときわ目を引く金彩は一見バカラのようだが本歌とは違い闊達で柔らかく、屈託がない。蓋のデザインも秀逸でとてもバランスが良いのに類例を知らず、もしかすると長崎あたりのキリスト教会で葡萄酒を配るのに注文した品かも知れない。
古くて良質なガラス作品には「懐かしさ」という感情とは別に、記憶の中の深い扉を開いてくれるような底力がある。それは「むかし」というやわらかい言葉の響きと同様、ガラスを透過した揺らめく光には産湯の中で見たような既視感、または陽性の記憶のようなものが存在している気がする。
昔のガラスは不純物が多く気泡だらけ。イビツ、だけど美しい。その美しさとは「美しいが不純物が多くてイビツ」という逆説をも包容する大らかさである。現代社会は効率偏重。不純物を限りなく排除し「清潔」な世界を目指している中東諸国、そして某国。果たして、時代は本当に進んだのだろうか。
大雪に聴きたい音楽
『European Standards』 Jan Lundgren Trio (ACT 9482-2)
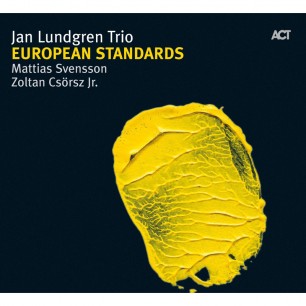 1990年代に入ってからジャズの世界が面白くなってきた。ジャズの本場、米国のみならず欧州各国からも優れたピアニストやコンポーザーが雨後の筍のように現れ、一時は欧州ジャズ・ブームが興ったのも記憶に新しい。中でもピアノ+コントランス(ベース)+ドラムで演奏されるピアノ・トリオの作品は構成がシンプルなだけに、アレンジや曲の解釈が様々で現代ジャズを楽しむ要素のひとつである。
1990年代に入ってからジャズの世界が面白くなってきた。ジャズの本場、米国のみならず欧州各国からも優れたピアニストやコンポーザーが雨後の筍のように現れ、一時は欧州ジャズ・ブームが興ったのも記憶に新しい。中でもピアノ+コントランス(ベース)+ドラムで演奏されるピアノ・トリオの作品は構成がシンプルなだけに、アレンジや曲の解釈が様々で現代ジャズを楽しむ要素のひとつである。
ここに紹介するヤン・ラングレン・トリオの作品は2009年のリリース。ヤン・ラングレンはスウェーデン生まれの若手ピアニスト。今や人気のピアニストの一人だが彼がACTレーベルに移籍して第三弾にして初となるピアノ・トリオ作品である。タイトル通り、ヨーロッパ各地のスタンダード曲を演奏した内容だが、全てグループ独自の解釈が反映されていて聴き飽きさせない。ACTというレーベルはジャズを軸に奇抜な作品が多いのだが、本作品はACTらしさを極めてエレガントな衣に包んで仕上げられており、特に5曲目のスイス民謡「Stets I Truure」は、犬雪車で雪原を一気に駆け抜けるような疾走感が素晴らしい。欧州ジャズ作品のもうひとつの魅力は音がいいこと。「いい音」の概念を言葉で説明するのは至難の業だ。ひとつ、この作品を手がかりとして欧州ジャズに触れてもらえれば嬉しい。
Bon Antiques展示会情報
12月7日(金)~9日(日)「Jikonka + Bon Antiques 展」
而今禾の西川さんとの古物展を東京で開催。花器を多めにセレクトする内容になると思います。
場所: Jikonka Tokyo(東京都世田谷区深沢 7-15-6)
時間:11:00~18:00まで
店主が全日在廊してお迎えします。



