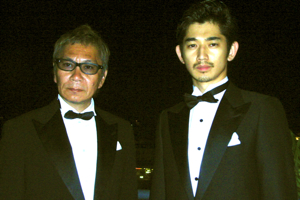2011年カンヌ映画祭でも「がんばれ日本」。日本映画の力と支える力。
(2011.05.31)パルムドールは『ツリー・オブ・ライフ』。
2011年カンヌ国際映画祭、最高賞にあたる、パルムドールを獲得した作品はブラッド・ピットとショーン・ペン主演の『ツリー・オブ・ライフ』でした。監督のテレンス・マリックは1978年に『天国の日々』でカンヌ国際映画祭監督賞を受賞するも、いったんは映画界から長く離れ、1998年に『シン・レッド・ライン』を発表。ベルリン国際映画祭金熊賞を受賞する才能を見せつけてきた伝説的存在です。歳月を経て、凱旋したことになる今年のカンヌで、みごと、パルム・ドールに輝いたのです。
ピッド演じる厳格な父のもとで子ども時代を送り成功した男を、ショーン・ペンが演じる心の旅。宇宙的でもあり、自然回帰的でもある美しい映像が際立つ、素晴らしい作品と評判です。
審査委員長のロバート・デ・二―ロを始め多くの審査委員たちが、観るなり、直感的に最高賞をイメージしたといいます。
出品するたび、主演女優が受賞。
カンヌ映画祭が才能を認め、世界的な評価を得た監督は再び新たな作品をカンヌで発表しますが、中でも、出品するたび、主演女優が、最優秀女優賞を獲得するという実績を記録した監督がいます。それは、ラース・フォン・トリアー監督。私も大好きなのですが、彼からは、目が離せません。『ダンサー・イン・ザ・ダーク』(00)のビョーク、『アンチ・クライスト』(09)のシャルロット・ゲンズブールが賞を獲得していますが、今回、フォントリア・ガールとなった『メランコリア(Merancholia)』キルスティン・ダンストも、みごと受賞。ジンクスが確かなものになったのです。
人気の高いアーチストを好きなだけ起用できる彼の才覚と、毎回意表をつくようなテーマに挑む才能は、天才肌。しかし、今回作品で使用していたワーグナーの曲が発端となり、フランスにとっては、第二次世界大戦の敵であるヒトラーを褒めた発言をしたと言うことが物議を醸し、審査員たちから映画祭追放を命じられるなど、とにかく、これもフォントリアーの側面です。
3月11日から2カ月後の5月11日に開催。
ことほどさように、華やかさも、厳しさも天下一品の、カンヌ映画祭ならではの話題はつきないのですが、何と言っても今年のカンヌは震災後の日本にとってはとても意味のある映画祭となりました。日本が、地震、津波、原発事故に見舞われた3月11日から、まさしく2カ月後の5月11日に開催されたカンヌ映画祭。後遺症の3重苦にあえぐ日本に、暖かい手を差しのべてくれたのです。映画を通じて、世界中の人たちが集まる場を有意義に使い、「頑張れ日本」キャンペーンが繰り広げられました。会場のあらゆるところに義援金の案内があり、キャンペーン・ガールも大活躍。出かけた日本人映画関係者は癒されっ放しでした。
そんな中、コンペティション部門に、三度ノミネートが叶った河瀬直美監督『朱花(はねづ)の月』、また、昨年のベネチア映画祭出品作品『十三人の刺客』に次いでの時代劇をひっさげ、三池崇史監督『一命』が、堂々の出品となりました。
さらに、監督週間部門には園子温監督『恋の罪』、短編部門にも田崎恵美監督『ふたりのウーテル』が選ばれるという快挙で、まさしく、がんばれ日本、がんばれ日本映画という、日本の底力を世界中に見せつけることが実現しました。
緑豊かな日本の風土が美しい『朱花の月』。
神の国日本を感じさせる奈良という場所にこだわり続け、『萌の朱雀』(97)でカンヌ映画祭監督週間でデビューし、初出品作品同士が競い合う、カメラドールを獲得。その後は『沙羅双樹』(03)でコンペ部門デビューを果たし、次いで、『殯(もがりの森』(07)でグランプリに輝くという、実力を発揮し続けて来た河瀬監督。今年の作品もまた、お約束の地、奈良にこだわっています。
どの作品にも共通して印象に残るのが、緑豊かな日本の風土。そこに息づく人々の営み。一見、荒々しさがないようなゆったりとした時の流れを映像に描きつつも、人の営みの断片は、いつも必ず優しいものだというわけではないことを感じさせるメッセージが心に残ります。
カンヌ映画祭お気に入りの、日本監督としての存在は大きく、上映後の会場に鳴り響いた拍手喝采は、日本の誇りとなるものでした。日本という国のこれからが見えにくくなっている今、これからの日本が、もう少しゆっくりと、本当に大切にしなくてはならないことは何なのかを考えながら前に進むべきでは、という意見を、作品上映の機会に述べた河瀬監督です。
日本人のルーツや日本人魂を伝える作品。
もともと、カンヌ映画祭での評価は、その国の持つアイデンティティーやオリジナリティーや民族性に注目し、こだわる視点があります。そういう点でも、今回、コンペ部門に正式出品となった二つの映画は、日本人のルーツや日本人魂を支える精神性を伝える作品ではなかったかと思うのです。
『一命』は、63年にカンヌに出品され、審査員特別賞に輝いた小林正樹監督『切腹』と同じ原作を再び映画化することのチャレンジです。そこには映画に対する大きなリスペクトがあるのです。『切腹』は緊張感漂う芸術性の高い作品として時代劇というジャンルを越え、武家社会、置きかえると日本人の縦割り社会至上主義を痛烈に批判するものでもありました。今回も、そのテーマは変わらないと思いますが、もっとわかりやすく、そのうえ3D仕様でもあります。日本建築の持つ奥行きを描くのに、3Dは効果的であるという考えのもと制作されたといいます。
ソワレで大注目、『一命』。
プロデューサー、ジェレミー・トーマスは、36回カンヌ映画祭出品作品でもある『戦場のクリスマス』(83)でいち早くビートたけしや坂本龍一を起用したことでもよく知られるが、いつも、敬意を持って日本との映画づくりを実現してきた存在です。日本復興支援に援助を惜しまない世界中の映画人たちに集ってもらい、震災後の東京国際映画祭開催を表明した、「ARIGATO(ありがとう) NIGHT」なるレセプションでも、日本応援のごあいさつにも駆けつけてくれました。
武士道というものは、欧米でも、日本の文化として大変に興味をもたれていることも事実で、私もよく、「腹きりってどうよ?」と、外国に行くたび聞かれたりしたものですが、理解できようが、できまいが、これが日本人精神のひとつなのだということの表現としては、エキゾチシズムも相まって、最大の話題となるものでしょう。みごと、「一命」のソワレは大注目され、チケットをとれなかったという参加者多数。会場は満杯状態となりました。これこそ、日本映画、そして日本の力のあらわれです。
瑛太演じる若い侍が竹光で腹を切るシーンになると、直視できないという外国人たちが少なくなかったようですが、切腹して果てた武士の義理の父親役の市川海老蔵の無念の思いを込めた所作に会場での感動は高まります。武士道だけを貫くのではなく、一人の人間としての尊厳というものに気づく生き方、それはまた、切腹とは別の死をも意味することでもあり、自分との戦いなのです。上映が終わると、長いスタンディング・オベーションが湧きおこりました。
歌舞伎の伝統に支えられた華やぎと演技のみごとさは、まさに日本の誇り、世界に誇れるものであることが明らかにされた上映会の夜でした。その他にも、日本の力を信じる各国の期待は冷めやらず、ある視点部門でも、シンガポールの監督エリック・クーが劇画作家の辰巳ヨシヒロの半生を描いた『TATSUMI(原題)』を出品上映。日本の漫画や劇画が大好きなフランスにも改めて注目されました。
また、同部門出品のガス・ヴァン・サント監督『永遠の僕たち(Restless)』には加瀬亮が、特攻隊で死んだ幽霊役で出演。日本を代表しての国際的活躍ぶりを見せてくれます。すでに邦題もついて、公開が待ち遠しいという声多数。
日本の熱い力を信じることが出来た、64回目のカンヌ国際映画祭でした。
カンヌ取材/まつかわゆま、加藤正美、三輪ここ
早くも公開が待たれる、ここにご紹介した映画の公開情報(一部未定の作品あり)
『ツリー・オブ・ライフ』 2011年8月12日(金)より丸の内ルーブルほか全国公開予定、 配給:ウォルト・ディズニー・スタジオ・ジャパン
『朱花(はねづ)の月』2011年9月3日 (土)よりユーロスペース、TOHOシネマズ橿原(かしはら)ほか公開予定、配給:組画
『一命』2011年10月ロードショー、配給:松竹
『恋の罪』2011年11月 テアトル新宿ほか公開予定、配給:日活
『永遠の僕たち』2011年12月公開予定 TOHOシネマズシャンテ、シネマライズほか全国公開予定、配給:ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント