転生の追憶 – 4 –
(2009.03.06)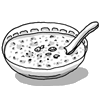
 |
九龍南端、散策道は夕暮れ。囁き合う恋人たちに混じり、美恵と上司である宮脇は、志津絵が御曹司から受けた卑劣な仕打ちに耳を傾けた。「いい考えがある。俺に任せてくれ」。翌朝、宮脇は志津絵の敵討ちに加担しようと、さっそくリーと言う名の怪しげな仕置き人を手配した。そして御曹司と妻が初夜を迎えたばかりの、仕置きの舞台となるリージェントホテルへと向かった。 |
◆ ◆ ◆
濃厚な香港での初夜の名残か、スゥイートルームの電話は、七回目のコール音を数えながら鳴り響く。ベッドの中から手を伸ばし、龍之介が受話器を上げた。
「おはようございます。張畑龍之介様ですか」宮脇が手配した、香港電子有限公司の社長になりすました、リー・キムホンからの電話だった。
リーは、日本の大事な取引先である張畑通商の次期社長が、新婚旅行で香港に立ち寄ったことを祝し、香港政庁の通商担当局長と共に、普林門でのささやかな昼食を用意していると。また社長である父上は、新婚旅行中にも関わらず、政府要人との懇親を深めようとする姿に、社業第一に励もうとされる次期社長の献身振りを、きっと評価されるであろうと、言葉巧みに誘った。
「それでも奥様一人ぼっちが心配ネ。私、考えがあります。リージェントホテルのエステティックサロンは、とっても豪華と世界中でも大変有名ヨ。だから私、奥様にエステをプレゼントしますネ。何も心配ない。だから安心」リーは寝惚け眼の龍之介を、ものの見事に丸め込んだ。
「ねぇ一体、何事なの? 」既にベッドから抜け出し、黒のナイティー一枚の姿で、窓際のソファーで足を組んだ玲華が呟いた。薄手のナイティー越しには、ほど良い形の胸元が透けて見え、龍之介は今すぐにでも、再びベッドに押し倒したい衝動に駆られた。
しかし龍之介の脳裏に、リーの言葉が駆け巡る。
次期社長の椅子は、生まれた時からのお約束だった。だからこれまで、人に負けても口惜しさすら感じたことがなかった。自分が腰掛ける社長の椅子は、自分から歩んでいかなくても、独りでに自分の行く前に用意されているものと、疑ったことなどなかった。しかし高度情報化の世となり、新しい価値観が生まれた。そして終身雇用制度も崩壊する時代となり、社員の会社に対する忠誠心は地に落ちてしまった。お家第一主義の家来という社員に傅かれていた、世襲制の時代に対して、逆風が吹荒れる世と変わり果てようとしている。さすがの龍之介も、その変化は敏感に感じ取っていた。だからリーからの電話は、願っても無いチャンス、何よりのお祝いの品と受け取ってしまったのだ。リーが助言したように、香港政庁の高官と太いパイプを作っておくことに、何の遜色も無い。張畑通商にとってリーの会社が、どれほどの売上高を誇る企業であるかなど、もともと会社の営業に認識の乏しい龍之介には、想いを巡らす余裕などなかった。
龍之介は渋る玲華を説き伏せ、ポットから二杯目のコーヒーを注いだ。
◆ ◆ ◆
リージェントの一階ロビーに、スーツを着込んだ龍之介が姿を現した。チェックインカウンター脇の観葉植物の陰に、宮脇と美恵、そして志津絵の三人は潜んだ。ホテルの正面入口に、黒塗りの大型リムジンが横付けされ、二人の紳士がドアマンに傅かれてロビーに入って来る。リーは予め写真で確認済みの、龍之介に声を掛けた。
「これはこれは若社長様。私、香港電子有限公司社長のリーです。お父様には大変お世話になっています」
「どうもはじめまして、張畑龍之介です」
「折角の新婚旅行中に、本当に申し訳ありません。こちらは、香港政庁のトン・ウェン通商担当局長です」
「張畑龍之介です。どうぞ宜しくお願いいたします」龍之介は深々と一礼し、握手を求めた。
「○ ○ ○ … ( 俺が通訳するから、お前は適当に何か言えばいい。とりあえず握手してやれ) … ○ ○ 」リーが龍之介の日本語を、広東語に訳しトンに伝えた。
「○ ○ ○ … ( リーさん、ちょっとネクタイが苦しくってかなわんよ) … ○ ○ ○ 」トンのボヤキを、すかさずリーは別の日本語に約した。
「お楽しみのご旅行中に、お時間をいただき恐縮です。しかし今回こうしてお逢いしたことにより、私達の関係は非常に良好なものとなるでしょうと、そうおっしゃっておられます」
龍之介は握手を交し、トンを見つめた。
整髪剤でオールバックに撫で付けた髪、小さめの銀縁眼鏡、青々しい髭剃り痕。どれをとっても寸分の隙も無い、理知的な政庁エリート高官だと龍之介は思った。ただ一つ、理知的な表情を和らげているのが、鼻の右脇にあるホクロだ。一見冷たそうに感じられる表情に、人間臭さを添えているようで、どことなく親しみが感じられる。
「ねぇ課長。あのトンって人、どっかで逢ったような気が… あのホクロ… 」美恵は怪訝そうにつぶやいた。
リーは龍之介とトンをリムジンに乗せ、普林門へと向った。
「ここはお父様を何度かお連れした、香港でもトップクラスのチャイニーズ・レストランです。日本の政財界の方が、香港においでになると必ずお立ち寄りになります」ボーイに案内され三人は個室に通された。「○ ○ ○ … ( あっちこっちギョロキョロするな! ゆったりと踏ん反り返ってればいい) … ○ ○ ○ 」テーブルの下に手を伸ばし、トンの太ももをつねりながらリーが笑顔でつぶやいた。
「○ ○ ○ … ( いゃあ、わしなんかこんな店入ったことねぇからさあ、つい興奮しちまって。スマンスマン) … ○ ○ ○ 」
「トンさんは、ここの蛇のスープがとてもお気に入りだそうです。とにかくアッチの方の精力が付いて効果満点だと。まだ新婚ホヤホヤの龍之介さんには、必要ないかも知れませんが。日本の政府関係の方は、必ずこれをお召し上がりになっておいでとか」リーはトンの言葉を、都合の良い日本語に訳して龍之介に告げた。
◆ ◆ ◆
リージェントホテル四階のエステティックサロンでは、アロマオイルが馥郁と薫る。ヒーリング効果の高い自然界の音が薄っすらと流れ、静かな時間が垂れ込めていた。窓の外には、百万ドルの夜景と歌われる香港島の高層ビル群がひしめきあっている。円の換金レートも自由化し、当時とは物価指数すら変わっていると思われるのに、未だ百万ドルの夜景と呼んでいるのはどうにも腑に落ちない。当時よりも百万ドル自体の価値が下がっているであろうに。
エステのベッドに横たわり、まどろみ行く思考の中を、玲華は彷徨い続けていた。
◆ ◆ ◆
龍之介と玲華の出かけた隙に、志津絵はデジカメを片手に、スゥイートルームのリビングに潜り込んだ。この後に繰り広げられるであろう、復讐劇を想像し得体の知れぬ快感に浸りながら。
◆ ◆ ◆
「お口に合いましたか? 香港一の広東料理の味は」リーは糊のきいた白いナプキンで、唇を拭いながら龍之介に尋ねた。
「ええ、そりゃあ勿論」
「○ ○ ○ … ( いゃあ、俺も本当今日まで生きてて良かったよ) … ○ ○ ○ 」
「トンさんは、お逢い出来たことで、香港と日本の関係が益々深まることを期待していますと、仰っておいでです」リーに促41されるように、トンと龍之介が握手を交わした。
「そうそう、後程お部屋の方に私からのお祝いの品を持って、セクレタリーがお届けに伺いますので、どうぞお楽しみに」
「いやっ、そんな。そこまでしていただいては」龍之介は社交辞令さながらの軽口で、恐縮そうな素振りを見せた。
「きっとお気に召すと思いますから」
普林門での会食を終え、リージェントにリムジンを向かわせながら、リーは意味ありげな笑みを洩らした。
◆ ◆ ◆
スゥィートに戻った龍之介を、まるで待ち伏せていたかのように、チャイムがせわしなく鳴り響いた。
「リーのセクレタリーで、メイと言います。リーから言付かってまいりました」ドアを開けると、濃厚な香水の薫りが押し入ってきた。グラマラスな肢体のメイは、香水の薫りを振り撒きながら、大きな包みを持って優雅に部屋の中へとやってきた。あまりに妖艶なメイの姿に、龍之介は立ち眩みを感じた。やっとのこと、冷蔵庫からビールを取り出し、メイにソファーを勧めた。
香港島の高層ビル群が、パノラマ写真のように広がる窓辺。まるでそのビューポイントを独り占めするかのように、デーンと置かれたライティングデスクの上で、電話の呼び出し音が鳴り響いた。