転生の追憶 – 6 –
(2009.03.25)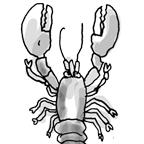
 |
仕掛け人リーが遣わした美女メイを前に、龍之介の心は騒ぎ出す。「メイを可愛がってやってください」。意味深な薄ら笑いを浮かべ、電話の向こうでリーがそうつぶやいたからだ。メイは龍之介の目を盗み、ビールのグラスに白い粉を溶かした。一方、高級エステでまどろみ、うっとりとした表情の妻玲華が部屋へと戻って来た。そこには!昨夜夫に愛されたベッドには、あられもない下着姿の女同士が、互いの身体を貪り合っているではないか! |
「そんなことがあってから、ちょっとノイローゼぎみになっちゃってたのかも知れないけど、いつもずっと誰かに付けられたり見られてる気がするの。そうそう、ここに来てからも時々… 」美恵はそう言ったと同時に、キッと鋭い視線で後ろを振り返った。
◆ ◆ ◆
宮脇は美恵を連れ、レパルスベイホテルへと続く、坂の下でタクシーを降りた。緩やかな坂道を二人はゆっくりと登っていった。
「ねぇ課長、結婚ってなんだろう。結婚って、それ程の意味があるのかしら。馬鹿よね。親の言うままに見合いして… 、この辺がそろそろ潮時かなって。周りも皆片付いていくし… 、この時期逃したら、私だけ取り残されそうで… 本当言うとそれが訳も無く怖かった。ずっとそんなことばっかり考えてたんだわ。あの人と歩むはずの将来とかなんて、まったくそっちのけで… 。だからバチが当ったのかな? 」美恵は舞台女優のように、長台詞のモノローグを、月のスポットを浴びながら滔々と続けた。
「結婚って言うブランド品があの時の私には必要だったの… きっと。両親から紹介された『幸せな結婚』という名のブランド品。ショーウィンドーの向こうで、絶妙のタイミングであの人が微笑みかけて来ただけ。最愛の人… 、そう思わなきゃあって。何でそんな風に考えたんだろう。バッカみたい!
でも良かった。ここへ来て。ちょっとショックだったけど、何か吹っ切れちゃったみたいだし。
わたし小さな頃から、あんまり自我がなかったの。だから人一倍、何でも人と一緒じゃないと気が済まなくって。洋服だって、髪型だって、お化粧も… 。中三の夏休み、みんなが恋人とA までしたって盛り上がって。わたしだけ何だか取り残された気になっちゃった。本当はファーストキスって、せつなくって一生心に残るものでしょう。でもわたしはゼンゼン。相手のことなんて、もうすっかり忘れちゃってるし。でももういいの。なんか疲れちゃったもん。人にはその人その人のスピードがあるのよ。わたしにはわたしのスピードが… 」美恵はまるで、芝居のクライマックスシーンを終えたかのように、大女優のような足取りで坂道を登って行く。
浜辺を見下ろす高台に、レパルスベイホテルのエントランスはあった。レンガ造りのショッピングモールはすべて閉まっている。
誰もいない真夜中の静寂。テラスのベンチに宮脇と美恵は並んで腰掛けた。
「課長! 覚えてますか? 社員研修のこと。わたし、のんびりやのグズだったから、レポート書くのにてこずって、終電なくなっちゃったのも気付かなかった… 。そしたら」
「俺がビールと牛丼、差し入れてやったんだっけ」
「そうそう! あんなに美味しかった牛丼、あれが最初で最後! 」
「相当腹へってたみたいだもんな。俺もあんな風に女子大出たての女の子が、無我夢中で遮二無二に牛丼がっついて、ビールで流し込んでる姿なんて初めて見たもの。まるで獣のようだった」
「でもあの日、本当はお子さんの誕生日だったんでしょう。後で志津絵先輩に教えてもらった」
「誕生日なんてこの国で、庶民が祝うようになってまだ一世紀もたってないんだ。それに我が子との誕生日は、まだまだこの先何十回とあるんだから。一回くらいゴメンナサイしても。それに俺にとっては、お前が無事研修終えて、ちゃんと配属されなきゃあ、こっちの方がお手上げの立場だったわけだし」
急に美恵が吹き出した。
「なんだよ、いきなり」
「知らなかったでしょう、本当のこと。告白っちゃおっかな? 」
「なんだよ、その告白っちゃうって」
「もったいないから、ずっと心の引き出しの一番奥にしまっておくつもりだったんだけどなあ」
「だから… 」「牛丼食べて、レポートやっとまとめ終えたら、もう終電なくなってたから、ホテルのバーへ連れてってくれたでしょ。あの後、部屋取ってくれたじゃない」
「それもみんな俺の自腹でな」「バーを出て部屋まで送ってくれたとき、課長がそのまま部屋に入って来てくれないかなって… 心の中で少しだけ期待してたの。本当は… 」
「… … … 」
「でもドアを開けたらクルッと踵を返して『おやすみ、明日遅れるなよ』だって。色気も素っ気もないったらありゃしないって感じ」
「本当の事言うと、あの時パンツに穴開いてるの思い出してさ。なぁんだもっと早く言ってくれたら、コンビニへひとっ走りして、新品に履き替えたのに」
「なによっ、今更… 」
「おいおい頼むよ。何でそんな大事なこと、あの時言ってくれなかったんだよ」
「あの時そう言ってたら、課長とわたしどうなってたんだろう? 」美恵は漆黒の水平線を見つめた。
「そうだなあ。でも今更どうしようもないな。どうあがいたって、三年前には戻れっこなんてないんだから」
「じゃあこうすれば? 」
美恵は宮脇を正面に見据えてそうつぶやき、ゆっくりと目を閉じ宮脇の唇を自分の唇で塞いだ。
◆ ◆ ◆
レパルスベイホテルの一室で、宮脇の携帯が鳴った。ベットの傍らで、美恵が寝返りを打った。宮脇は窓を開けベランダに出て携帯を受けた。
「やっぱり… そういうことか。ありがとうミスター・リー」美恵を起さぬように、静かに部屋の中へと戻った。
美恵は枕もとで半身を起しながら、気だるそうにつぶやいた。
「わたし、女としての魅力が欠けてる? 」
「そうじゃない」
「だって… 」美恵が涙ぐんだ。
「君は十分すぎるほど魅力的だ。君が新入社員として入社してきた時から、ずっと気になっていた。だから研修会で遅くなった夜は、正直しめたと思った。しかし… 」
「しかし、パンツに穴が開いてたから? 」
「いや… それもそうなんだが。… 既にぼくには家族がいたし」
「わたしだってそんなこと最初から判ってた。それに今だってちゃんと判ってる。わたし課長の奥さんにして欲しいなんて、これっぽっちも… 。でも… あの夜と、そして昨日の夜はどうしてもあなたに抱かれたかった… ただそれだけ」
部屋のチャイムが鳴り響いた。朝食のルームサービスが、厳かに運び入れられた。ベランダにあるオープンエアのテーブルで、宮脇はゆっくりとコーヒーを口に運んだ。美恵はパンケーキにたっぷりとシロップを垂らしている。
「君は、前世って信じるかい? 」
「輪廻転生のようなものでしょ」
「うん。人間の魂ってのは、この世に何度も何度も生まれてくるんだ。そして今君の魂は、君の肉体を借りている。ぼくだって同じだ。過去に何度も何度も生まれ変わって来た記憶を、魂はちゃんと記憶しているんだってさ。アメリカの著名な精神科医が治療に用いた催眠療法で、多くの患者が遠い過去の記憶を鮮明に蘇らせたという事例も報告されている。その医師によると、魂は何度も何度も別の時代に、まったく違う国に生まれ変わる中、いつの時代でも自分の身近に現われる仲間の魂と出逢うんだそうだ。時にはそれが自分の夫としてだったり、別の時代では自分が現在の夫の子供だったり、或いは自分が夫で現在の夫が妻になる場合だってあるという。それをその医者は、ソウル・メイト、つまり魂の仲間と呼んでいる。ソウル・メイトは互いに何らかの関係を保ちながら、互いの魂が成長し合うように影響力を持つ。またソウル・メイトには、善人ばかりとは限らず悪役も含まれているんだ。つまり三角関係の妻と愛人の場合とか。前世では愛人と夫が夫婦で、そこに現在の妻が横恋慕して三角関係になっていたとか。魂はこの世に生まれ出でる前に、今生で何を学ぶか自分でテーマを決めるそうなんだ。例えば『愛人として自分の気持ちを押し殺して、日陰で生き抜くという試練を学ぶため』だったりとか」
「じゃあ、それが今の私? 」
「ちょっと待てよ。そう結論を急ぐものじゃない。自分の魂が今生において描いたシナリオは、残念ながら現世をこうして生きている、君やぼくにはわからないのさ。ぼくらにとってはまるで『偶然が紡ぎ合わされたような人生だった』としても、それが今際いまわの際きわになって初めて自分の魂が予め描いたシナリオだったと気付くかも知れないけど」