土屋孝元のお洒落奇譚。日本は出汁の国?
(2011.01.12)年始という事もあり、出汁について考えたいと思います。
鰹節、昆布、いりこ(煮干)、アゴ(飛魚)、鯛の頭、鰤のアラ、干し椎茸、
干し海老、鶏ガラ、干し貝柱、オックステイル、豚骨……。
まだまだあると思うのですが、ざっと頭に浮かぶのはこのくらいでしょうか。
これは、ラーメンのスープの具材に近いモノではないですか。
最近の流行りは 魚介系、動物系のダブルスープとか、野菜の出汁も必要ですね。
玉葱、人参、セロリ、ネギ、ニンニク、ショウガ、みんな良い出汁が出ます。
蕎麦での返しにあたる、醤油ダレも必要です。
醤油も溜まり醤油、しょっつる、出汁醤油、白醤油、
関東風の濃口醤油、関西風の薄口醤油といろいろとありますね。
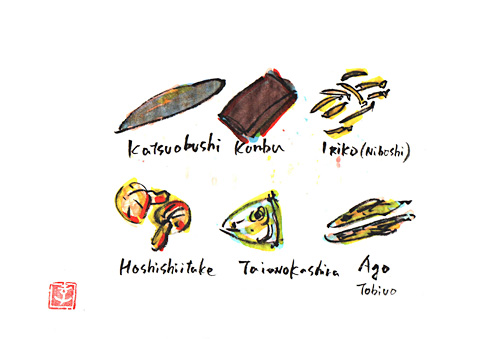 |
| ©Takayoshi Tsuchiya |
ラーメン文化は日本独特のもので、世界に誇れるものではないでしょうか。
これだけの食文化のある国は、世界中見ても あまりないのではと思います。
世界で一番ミシュランの星の多い国、それだけはでなく、
各地方それぞれにより醤油や味噌や出汁が違う文化、
一番わかりやすい例がお雑煮です。
関東風(江戸風)は鰹出汁に醤油のすまし汁風、
で、それに焼いた角餅を入れますね、
わが家では鳥肉も加えます。
関西、京都では白味噌仕立て丸餅を焼かないで入れます。
この関東風と関西風の境になるのが、
岐阜の関ヶ原あたりと言われています。
この雑煮でもユニークなのは、徳島の丸餅に小豆餡を入れて
焼かずに白味噌仕立の雑煮ですね、
新潟では鰤を入れる所もあるようです。
東北地方では生イクラを入れたりします。
九州では丸餅を焼いて入れる所もありますね。
この様に雑煮一つでも、地方によりそれぞれ違いが明確にあり、
日本の食文化、出汁文化は優れています。
お雑煮に次いでおせちです。ここで我が家で作る、と言うか自分で作る、
フライパン(北京鍋があればそれで)一つでも出来る簡単な煮物のレシピを。
鳥胸肉ともも肉、ごぼう、人参、レンコン、竹の子、干し椎茸、コンニャク、
人数に合わせ材料も適量に、ごぼうとコンニャクは多いほうが良いですね。
ゴボウ(皮付きゴボウは良い味になります)はよく洗い皮ごと乱切りに、
レンコンは一度湯通しする、
このときにお酢を少量入れるとより白くなります。
竹の子は水煮で大丈夫です、ざっと湯通しをしたほうがよいでしょうね。
コンニャクは手でちぎります(こうする事で断面を多くして味が浸み込むようになります)
その後、湯通ししておきます。
干し椎茸は水で戻しておく、
1日以上はおいて置いたほうが良いでしょうか。
 |
| ©Takayoshi Tsuchiya |
人参も皮をむいて乱切りに、まず、フライパンを熱くしてから、
オリーブオイル(エキストラバージンオイルでなくともかまいません)を入れ、
鳥肉、ゴボウを炒めます。
この鳥肉とごぼうは相性が良く、良い感じで旨味が増します。
ある程度火を入れてから、次に硬い具材(竹の子、人参、)を入れ炒めます。
ここで出汁(昆布は利尻のものを水から入れて、お湯が湧いたら
厚削りの鰹節を入れすぐに濾し出しを取ります。一番だしですね)
を入れて煮込み始めます。干し椎茸、コンニャクも入れます。
次に酒をお好みで入れます。多く入れると具材が柔らかく仕上がります。
味醂も加えます。
砂糖(甜菜糖があればそれが良いでしょう)を具材の量に合わせてお好みで入れ、
醤油(溜まり醤油、薄口醤油)を入れます。
最後に仕上げに干し椎茸の戻し汁を入れます。
あとは、好みで味付けを調整していただけば、良いと思います。
煮込む時間は30分ぐらいでしょうか。
飾りに塩茹でしたさやえんどうを飾り出来上がりです。
干し椎茸の戻し汁は、出汁に加えて何にでも使えて重宝します。
使う量は少なめに、香りが強いので、好き嫌いがあるでしょうから。
里芋煮なども出汁と干し椎茸の戻し汁で美味しくなりますね。
椎茸煮については、今はなき歌舞伎座前、
木挽町『辨松(べんまつ)』の弁当の味が好きなので、少し甘めに仕上げます。
歌舞伎見物に出かける時には、いつも、『辨松』の弁当を買ってから出かけました。
泉鏡花の『天守物語』や『海獣別荘』、面白かったなあ。
話を戻し、先ほどの煮物は溜まり醤油は少なめに、隠し味という感じで、
全体の仕上りの色を綺麗に仕上げるには、
薄口醤油で仕上げたほうが良いですね。